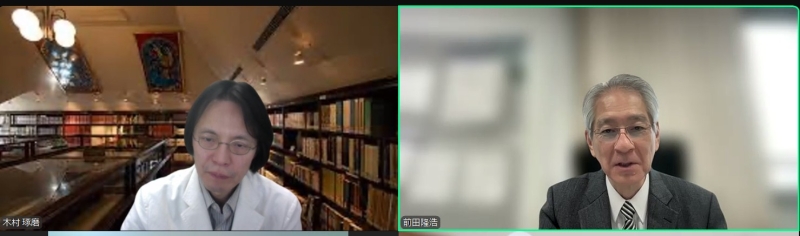ニュース
大学ネットワーク
2024年JPCA英文学会誌 掲載論文<筆頭著者インタビュー>東京科学大学 総合診療科 木村 琢磨先生
大学ネットワーク委員会では、2024年にJPCA英文学会誌(Journal of General and Family Medicine)に掲載された論文の中からJPCA大学ネットワーク委員会として注目すべき論文について、筆頭著者の先生へインタビューを行いました。今回は「The characteristics of general practitioners and geriatricians who take overall responsibility for the care of older patients with multimorbidity
(「マルチモビディティ」(「多疾患併存」)の高齢患者のケア全体を責任を持って担当する総合診療医と老年医学専門医の特徴)」の論文を発表された、東京科学大学 医学部 総合診療科 木村琢磨先生にお話しを伺いました。
(「マルチモビディティ」(「多疾患併存」)の高齢患者のケア全体を責任を持って担当する総合診療医と老年医学専門医の特徴)」の論文を発表された、東京科学大学 医学部 総合診療科 木村琢磨先生にお話しを伺いました。
論文データ
論文タイトル
The characteristics of general practitioners and geriatricians who take overall responsibility for the care of older patients with multimorbidity
(「多疾患併存」の高齢患者のケア全体を責任を持って担当する総合診療医と老年医学専門医の特徴)
(「多疾患併存」の高齢患者のケア全体を責任を持って担当する総合診療医と老年医学専門医の特徴)
筆頭著者
東京科学大学 医学部 総合診療科 木村琢磨先生
― 背景
「多疾患併存」の高齢患者は、複数の医師、複数の医療機関を受診することがよくあり、ケア全体について責任を負う主治医がいることは有益である可能性があります。この研究では、「多疾患併存」の高齢患者の診療について、ケア全体に責任を持つことが多い総合診療医と老年医学専門医の特徴を明らかにするための調査を実施しました。
― 研究手法
2022年6月に国内の家庭医療専門医・プライマリ・ケア認定医、老年科専門医、合計3300名に無記名の質問票調査を郵送法で行いました。「多疾患併存」の高齢患者における診療において、困難な疾患・患者背景、重視する臨床要素・診療マネージメントに関する項目を4段階リッカート尺度で採点し、修正ポアソン回帰分析を用いて、「多疾患併存」の高齢患者の診療について、ケア全体に責任を持つことが頻繁であると回答したことと関連する因子を特定しました。質問票で回答者の性別、年齢、医師経験年数、勤務先(無床診療所、有床診療所、200床未満の病院、200床以上の病院、大学病院など)、診療内容(外来診療、訪問診療、介護施設、病棟診療)、勤務先の人口規模のなどの人口統計学的データも尋ねました。65~74歳、75~89歳、90歳以上、各年齢層を診療する頻度についての質問も設けました。
― 結果
746人の医師データを分析し、「多疾患併存」の高齢患者の診療において、ケア全体に責任を持つことが多い総合診療医と老年医学専門医の特徴として、病棟診療、訪問診療に関与し、90歳以上を診療する頻度が多く、「多疾患併存」の高齢患者における診療において、様々な診療マネージメントを行っていることが示されました。
― この研究に取り組まれた経緯を教えていただけますか?
JPCA(日本プライマリ・ケア連合学会)の委員会の一つで、私自身も立ち上げに携わらせていただいた「高齢者医療委員会(現:高齢者医療・在宅医療委員会)」の活動が基盤になっています。この委員会は「日本老年医学会」の協力で誕生し、立ち上げ当初から取り組んできたテーマの一つがマルチモビディティ(「多疾患併存」)でした。複数の疾患を有する高齢者の方々の問題点の抽出や現状調査などを委員会の中でチームを作って取り組んできました。本論文の調査に着手したのは2022年ですが、それまでの委員会での議論が非常に役立ちました。
― 今回の研究で明らかにしたかったことは何でしょう?
ご存知のようにプライマリ・ケアの定義の一つに「ACCCA」があります。A(Accessibility)=近接性、C(Comprehensiveness)=包括性、C(Coordination)=協調性、C(Continuity)=継続性、A(Accountability)=責任性の5つを指す言葉ですが、この中で「責任性」が特に分かりにくいと感じてきました。説明責任、診療責任など多面的な意味合いが含まれるとされますが、曖昧です。そこで、高齢者の「多疾患併存」患者への「責任性」を医師がどのように捉えているのか、実態を調査・整理したいと考えました。
― 調査方法のポイントは?
臨床データから責任性を測定するのは現実的ではないと判断し、医師への質問票調査を行うこととしました。質問票を郵送した医師は計3300人。内訳はJPCAに所属する家庭医療専門医、プライマリ・ケア認定医から無作為に抽出した1650人、日本老年医学会に所属する全員の老年医学専門医1650人です。質問票では、「多疾患併存」の高齢患者の診療において、診療困難となる疾患・患者背景、重視する臨床要素・診療マネージメントなどを調査しました。有効回答は836人、最終分析数は746人となりました。
― 結果で意外だった点はありますか?
「多疾患併存」の高齢患者の診療におけるケア全体を責任について、「頻繁に」責任を負っていると回答した医師が69.6%いる一方で、「時々」という回答が26.8%、「あまりない」「まったくない」が併せて3.6%いることに驚きました。責任性においてあまり積極的と言えない約3割の理由や背景を探ることが、今後の課題解決の糸口になり得る可能性を感じました。
― 「頻繁に」責任を負っている約7割の特徴は?
「頻繁に」責任を負っているグループは病棟診療、訪問診療に関与し、90歳以上を診療する頻度が多いことが明らかになりました。これは私の臨床経験に基づく考察になりますが、例えば、90歳以上など、高齢になるほど疾患が多くなり、病棟診療、訪問診療では複合的なサポート、包括的なケアが必要になります。その存在を家庭医療専門医、プライマリ・ケア認定医、老年医学専門医も強く感じているのだと思います。これらを患者と共有する、つまり、患者側と医師側の双方に主治医としての合意形成がある前提が、責任性を高めるポイントと言えるかも知れません。
― 責任性の意識が高い医師が増えていくために、何が必要でしょうか?
フレイルや認知症などの影響で医療機関へ通うことが困難になる高齢者の「多疾患併存」患者は、今後さらに増加するでしょう。診療で困難になやすい臨床背景に対する教育・研修を充実させるなど、「多疾患併存」診療の体制づくりを整えることで、責任性の意識が高い家庭医や総合診療医、老年内科医が自然に増えていくのではないでしょうか。
― 診療ガイドラインのような指針を示すことも有効?
例えば、日本老年医学会と日本糖尿病学会が作成された「高齢者糖尿病診療ガイドライン」の血糖コントロール目標のように、高齢者特有の問題点なども踏まえた「多疾患併存」診療の手引書があれば、多くの医師の手助けになり得ると考えます。
医学生・研修医・専攻医の時こそ研究に触れる場を
― 研究について、若手医師へのアドバイスをお願いします。
私自身、素晴らしいメンターの先生たちにご指導いただけたから今があります。とくに、本研究でもご指導を頂いた、JPCAの監事でもある松村真司先生には学生時代からお世話になっております。やはり、メンターの存在が研究において非常に重要であると思います。とくに、家庭医・総合診療医として臨床の現場にいつつ、かつ研究も手掛けている方と出会えると、様々な知見や手法をご指南いただきやすいと思います。
― どうすればメンターの先生と出会いやすいでしょうか?
現在は、様々な大学で総合診療・家庭医療、地域医療に関する講座があります。そうした講座へ、意識的に出向くとご縁が生まれやすいでしょうね。また、JPCAでは、様々な学術団体とのジョイントセッションがありますので、横断的に他領域の先生たちと繋がりを持つことも自分の研究に必ず生きてくると思います。私自身、今回の研究で共同研究者である新村健先生や橋本正良先生にご指導いただき、総合診療と共に老年医学の要素を論文に入れたことで、より学術的な内容にブラッシュアップすることができました。私自身、大学に拠点を移して約10年が経ちますが、意外な場所で理解者や協力者と出会い、研究や論文の突破口を見つけられるものだと実感しています。
― PBRN(Practice Based Research Network)については、どう思われますか?
PBRNの目的は、医療機関と研究機関をリンクさせてプライマリ・ケアの診療に役立つ研究を推し進め、医療の質を高めることにあると理解しております。例えば、学会主導の統計調査データを集めている学術団体もあるときいています。診療データを蓄積することは、プライマリ・ケアの医療の質向上と若手医師・研究者の育成において非常に有意義だと考えます。
― 研究に触れる場を増やすことが大切なのですね。
最近は、どちらの大学でも研究室に所属して学んでいる学生が多いと思います。東京科学大学でも、本研究や、在宅医療におけるコミュニケーションなど私の研究に、「このようなテーマが研究になるとは思わなかった」「こんな解析が存在するなんて」と何気ないきっかけで研究に興味を持ってくれる学生が少なからずいます。また、在学中からJPCAの学生セッションで発表することは、学生だけではなく学会にとっても重要だと感じています。医学生や若い医師が集まる学会には活気が生まれ、それが新しい時流を生むエネルギーになります。来年度も学生さんと一緒に研究をして学生セッションで発表できたらと思っています。
取材協力者プロフィール
東京科学大学 医学部 総合診療科
木村琢磨(きむら たくま)
<木村先生の論文>
JPCA英文学会誌掲載論文
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgf2.727
【経歴】
1997年3月 東邦大学医学部 卒業
1997年4月 国立東京第二病院 総合診療方式 研修医
1999年4月 国立病院 東京医療センター 総合診療科 レジデント
2001年4月 国立療養所 東埼玉病院 内科 医員
2002年4月 国立病院 東京医療センター 総合診療科 医員
2006年4月 国立病院機構 東埼玉病院 総合診療科 医員、医長
2008年4月 国立病院機構 東埼玉病院 総合診療科 医長
2010年10月 豪州ニューカッスル大学大学院 臨床疫学修士課程(distant learning)修了
2012年3月 東邦大学大学院 医学研究科博士課程 修了
2012年4月 三重県立一志病院 家庭医診療科 部長
2013年7月 北里大学医学部 講師、准教授(総合診療医学)
2014年1月 北里大学医学部 准教授(総合診療医学)
2018年1月 北里大学医学部 教授(新世紀医療開発センター 地域総合医療学)
2019年5月 埼玉医科大学医学部 教授(総合診療内科)
2023年4月 東京医科歯科大学 介護・在宅医療連携システム開発学講座 教授/ 総合診療科 特任教授
2024年10月 東京科学大学(名称変更)介護・在宅医療連携システム開発学講座 教授/ 総合診療科 特任教授
【資格・免許】
日本プライマリ・ケア連合学会 認定医・指導医
日本内科学会 認定医・総合内科専門医・指導医
日本在宅医療連合学会 在宅医療専門医・指導医
日本老年医学会 老年病専門医・指導医
日本感染症学会 感染症専門医
【所属学会】
日本プライマリ・ケア連合学会
日本内科学会
日本在宅医療連合学会
日本老年医学会
日本感染症学会
木村琢磨(きむら たくま)
<木村先生の論文>
JPCA英文学会誌掲載論文
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgf2.727
【経歴】
1997年3月 東邦大学医学部 卒業
1997年4月 国立東京第二病院 総合診療方式 研修医
1999年4月 国立病院 東京医療センター 総合診療科 レジデント
2001年4月 国立療養所 東埼玉病院 内科 医員
2002年4月 国立病院 東京医療センター 総合診療科 医員
2006年4月 国立病院機構 東埼玉病院 総合診療科 医員、医長
2008年4月 国立病院機構 東埼玉病院 総合診療科 医長
2010年10月 豪州ニューカッスル大学大学院 臨床疫学修士課程(distant learning)修了
2012年3月 東邦大学大学院 医学研究科博士課程 修了
2012年4月 三重県立一志病院 家庭医診療科 部長
2013年7月 北里大学医学部 講師、准教授(総合診療医学)
2014年1月 北里大学医学部 准教授(総合診療医学)
2018年1月 北里大学医学部 教授(新世紀医療開発センター 地域総合医療学)
2019年5月 埼玉医科大学医学部 教授(総合診療内科)
2023年4月 東京医科歯科大学 介護・在宅医療連携システム開発学講座 教授/ 総合診療科 特任教授
2024年10月 東京科学大学(名称変更)介護・在宅医療連携システム開発学講座 教授/ 総合診療科 特任教授
【資格・免許】
日本プライマリ・ケア連合学会 認定医・指導医
日本内科学会 認定医・総合内科専門医・指導医
日本在宅医療連合学会 在宅医療専門医・指導医
日本老年医学会 老年病専門医・指導医
日本感染症学会 感染症専門医
【所属学会】
日本プライマリ・ケア連合学会
日本内科学会
日本在宅医療連合学会
日本老年医学会
日本感染症学会
インタビュワー
大学ネットワーク委員会 前田隆浩
最終更新:2025年03月30日 00時00分