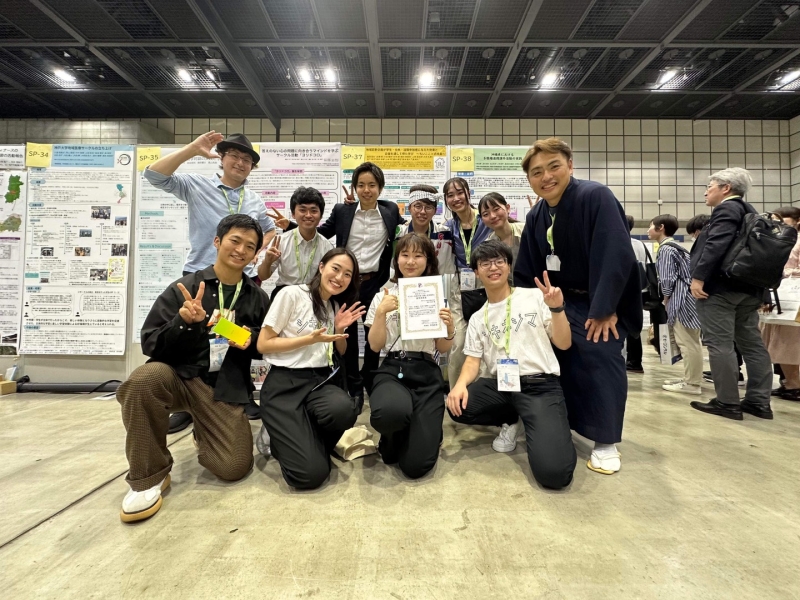ニュース
大学ネットワーク
第15回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 学生セッション 受賞者インタビューVol.8 <ポスター発表の部 優秀発表賞> 神戸大学医学部
2024年6月7日(金)〜9日(日)アクトシティ浜松で開催された第15回 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会学生セッション。口演発表24エントリー、ポスター発表47エントリーの中から、各部門で受賞された発表内容をご紹介します。今回は「ポスター発表の部」で優秀発表賞を獲得した「地域診断企画が学生・住民・遠隔参加者に与えた効果と企画を通して得た学び ~ちいここ×式根島~」のメンバーである、神戸大学医学部医学科の島津里彩さん、橋本麻里奈さん、島根大学医学部医学科の上西凜太郎さん、活動時は上智大学総合グローバル学部の大谷理歩さん(現在、社会人)、そしてその活動をサポートされた阪本直人先生、奥知久先生からお話をうかがいました。
ポスター発表の部 優秀発表賞
##受賞内容
ポスター発表の部 優秀発表賞
##演題名
地域診断企画が学生・住民・遠隔参加者に与えた効果と企画を通して得た学び ~ちいここ×式根島~
##大学
神戸大学医学部
##発表者名
島津里彩さん(神戸大学医学部医学科3年)
##指導者名
岩瀬翔先生(前・式根島診療所長、現・神津島村国民健康保険直営診療所長)
阪本直人先生(筑波大学 医学医療系)
奥知久先生(医療法人ぼちぼち会おく内科・在宅クリニック)
ポスター発表の部 優秀発表賞
##演題名
地域診断企画が学生・住民・遠隔参加者に与えた効果と企画を通して得た学び ~ちいここ×式根島~
##大学
神戸大学医学部
##発表者名
島津里彩さん(神戸大学医学部医学科3年)
##指導者名
岩瀬翔先生(前・式根島診療所長、現・神津島村国民健康保険直営診療所長)
阪本直人先生(筑波大学 医学医療系)
奥知久先生(医療法人ぼちぼち会おく内科・在宅クリニック)
『地域診断企画が学生・住民・遠隔参加者に与えた効果と企画を通して得た学び ~ちいここ×式根島~』
近年、医療者が地域の特性を知り、健康の社会的決定要因(SDH)と地域の健康課題との関係を理解することの重要性が高まっている。それを受けて全国各地の医療現場では地域にアプローチする様々な取り組みが実践されている。しかし医療系学生が学校教育の中で地域の特性を体験し学びを得る機会は少ない。そこで、式根島診療所と学生団体「ちいここ」が、多世代・多業種を巻き込んだ式根島での地域診断企画を共催した。本企画の内容と効果、その過程で学生が新たに学んだ視点や葛藤について報告する。
学生と診療所のコラボ企画
今回の発表は「ちいここ」というオンラインコミュニティと「新島村国民健康保険式根島診療所(以下、式根島診療所)」が共同で行った地域診断企画の内容等をお伝えするものです。まず、「ちいここ」について説明すると、これは地域医療に関心のある医療系の学生たちが集まるオンラインコミュニティのことで、9名のメンバーで運営。現在、日本全国から100名以上の学生たちが集まるコミュニティとなっています。主にオンラインでの勉強会や交流会、地域医療に関する情報共有、地域医療の最前線の現場を体感する合宿といった活動をしています。
今回、その活動の一環で行うことにしたのが式根島の地域診断です。その際、ご協力いただいたのが同島の式根診療所所長の岩瀬翔先生でした。式根島の地域診断をしたいという私たちの希望に対して、岩瀬先生は快諾してくださり、企画が動き始めました。
今回、その活動の一環で行うことにしたのが式根島の地域診断です。その際、ご協力いただいたのが同島の式根診療所所長の岩瀬翔先生でした。式根島の地域診断をしたいという私たちの希望に対して、岩瀬先生は快諾してくださり、企画が動き始めました。
オンライン地域診断イベント
地域診断とは「対象の地域の課題や資源からその地域の特徴を明らかにし、健康な暮らしに結びつけていく」というものです。今回の企画では半年間にわたって、全国の多世代・多業種のべ50人以上が集まる2回のオンライン地域診断イベント、学生による式根島フィールドワーク、島民向けオンライン報告会と現地ワークショップを実施しました。
その内容ですが、まずオンライン地域診断イベントについては参加者同士の意見交換や式根島特有の課題の掘り起こし、島や地域に共通する普遍的な課題などを話し合いました。このイベントに参加する前は「式根島について全く知らない」という人が50パーセント(15人)にのぼりましたが、イベントを経て「同島に関わり続けたい」と回答した人が93.2パーセント(28人)を数えました。
その内容ですが、まずオンライン地域診断イベントについては参加者同士の意見交換や式根島特有の課題の掘り起こし、島や地域に共通する普遍的な課題などを話し合いました。このイベントに参加する前は「式根島について全く知らない」という人が50パーセント(15人)にのぼりましたが、イベントを経て「同島に関わり続けたい」と回答した人が93.2パーセント(28人)を数えました。
CAPモデルで地域を見つめる
一方、式根島のフィールドワークに関してはまずCAPモデル(community as partner model)を用いて島の全体像を捉えることにしました。CAPモデルとは地域診断を行う際の枠組みのことで、地域社会を8つの観点(保健医療と社会福祉・政治と行政・安全と交通・教育・物理的環境・レクリエーション・経済・コミュニケーション)から見つめることによって全体像を捉えるという手法です。式根島の場合、例えば「保健医療と社会福祉」という観点から見ると「ケアマネはいない」「医師は1年交代」といった要素が出てきています。
さらに現地における実地調査を通じては、それまで表面的に捉えていた島の魅力や課題の背景を理解でき、また潜在的な魅力や課題に気づくこともできました。例えば、島の濃密な人間関係を魅力と捉えていましたが、島の人たちの中にはそれが負担(課題)になっていることがわかったケースがあげられます。こうした結果をもとに改めてオンラインで地域診断イベントを開催し、話し合った内容を島民の方々へ報告しました。
さらに現地における実地調査を通じては、それまで表面的に捉えていた島の魅力や課題の背景を理解でき、また潜在的な魅力や課題に気づくこともできました。例えば、島の濃密な人間関係を魅力と捉えていましたが、島の人たちの中にはそれが負担(課題)になっていることがわかったケースがあげられます。こうした結果をもとに改めてオンラインで地域診断イベントを開催し、話し合った内容を島民の方々へ報告しました。
島民主体のまちづくりもスタート
今回の地域診断企画をきっかけに、式根島の住民の方々による島民主体のまちづくり活動が始まりました。学生たちが気づいた式根島の魅力や課題をもとに今後の島づくりを考えるワークショップが開催され、それは「式根島よっちき会議」の結成につながりました。もともとは岩瀬先生たちが行っていた「式根島おせっかい会議」という活動に新たに加わったという形です。「よっちき」とは「寄っていきなよ」という意味の島の方言で、会議の目的は「一緒に楽しく繋がることによって、自分たちの力で健康になれる場づくり」となりました。
以上のことを踏まえ、私たちが今後の展望として思い描いているのは、今回のような実地調査とオンラインイベントを組み合わせた地域診断経験を他のエリアにも広げること。そのことで「地域の暮らしや地域医療に関心のある学生と地域診断の体験や学びを深める」「多世代・多職種が繋がり、それぞれが自身の活動地域を顧みる場をつくる」といったことに取り組んでいきたいと考えています。
以上のことを踏まえ、私たちが今後の展望として思い描いているのは、今回のような実地調査とオンラインイベントを組み合わせた地域診断経験を他のエリアにも広げること。そのことで「地域の暮らしや地域医療に関心のある学生と地域診断の体験や学びを深める」「多世代・多職種が繋がり、それぞれが自身の活動地域を顧みる場をつくる」といったことに取り組んでいきたいと考えています。
― 今回どのような経緯で式根島の地域診断に取り組むことになったのでしょうか?
島津:私たちが運営するちいここは地域医療に関心を持つ医療系学生の集まりで、これまでいろんな地域において合宿をしてきました。当然、離島の医療にも興味を持っていて「いつかチャンスがあれば島での合宿もしてみたい」と思っていたんです。
そんな折、2023年のプライマリ・ケア連合学会の集まりで阪本先生からご紹介いただいたのが岩瀬先生です。当時、岩瀬先生は式根島で働いておられて、せっかくご縁ができたということもあり、次の合宿の舞台を式根島にという流れになりました。
当初は地域診断をするという考えはなかったのですが、「より深い学びを得るためにはどうすればいいか?」と話し合いをしている中で、阪本先生から「地域診断という手法がありますよ」とアドバイスをいただきました。それがきっかけで式根島の地域診断を実施することになったわけです。私自身は都市部で生まれ育ったので、離島での暮らしがどういうものなのかにとても興味がありました。
そんな折、2023年のプライマリ・ケア連合学会の集まりで阪本先生からご紹介いただいたのが岩瀬先生です。当時、岩瀬先生は式根島で働いておられて、せっかくご縁ができたということもあり、次の合宿の舞台を式根島にという流れになりました。
当初は地域診断をするという考えはなかったのですが、「より深い学びを得るためにはどうすればいいか?」と話し合いをしている中で、阪本先生から「地域診断という手法がありますよ」とアドバイスをいただきました。それがきっかけで式根島の地域診断を実施することになったわけです。私自身は都市部で生まれ育ったので、離島での暮らしがどういうものなのかにとても興味がありました。
― 実際に地域診断を行ってみての感想はいかがでしたか?
島津:地域診断というと現地のフィールドワークがメインという先入観があったのですが、今回はその前後でオンラインのイベントを行いました。事前学習をしたり、フィールドワーク後に改めてディスカッションを行うことで学びが深まった印象です。オンラインでは様々な地域から参加した学生や教員など社会人と意見交換できたのがとても貴重な経験となりました。
現地のフィールドワークに関しては岩瀬先生から地域活動のキーパーソンとなりうる住民の方につないでいただいて、およそ20名の皆さんからお話を伺うことができました。井戸端会議に混ぜてもらったり、ゲートボール大会に参加させてもらったりしました(笑)。
大谷:現地に行って印象的だったのは、表面的な枠組みだけでは捉えきれない島民の思いや状況があるということです。
式根島は新島という島と合わせて「新島村」という自治体になっているのですが、その新島との格差を気にする島民の方もいらっしゃいました。地域格差を考えるとき、私たちはどうしても「都市と地方」という大きな枠組みで見ようとしますが、それ以外に 「東京でありながら離島の式根島」、「新島村の中の式根島」という単純な都市と地方という枠組みでは捉えきれないものがあるのだと気づかされました。島で生まれ育った人なのか、島への移住者なのかという点でも、島の課題や魅力の捉え方は変わってくるようでした。
現地のフィールドワークに関しては岩瀬先生から地域活動のキーパーソンとなりうる住民の方につないでいただいて、およそ20名の皆さんからお話を伺うことができました。井戸端会議に混ぜてもらったり、ゲートボール大会に参加させてもらったりしました(笑)。
大谷:現地に行って印象的だったのは、表面的な枠組みだけでは捉えきれない島民の思いや状況があるということです。
式根島は新島という島と合わせて「新島村」という自治体になっているのですが、その新島との格差を気にする島民の方もいらっしゃいました。地域格差を考えるとき、私たちはどうしても「都市と地方」という大きな枠組みで見ようとしますが、それ以外に 「東京でありながら離島の式根島」、「新島村の中の式根島」という単純な都市と地方という枠組みでは捉えきれないものがあるのだと気づかされました。島で生まれ育った人なのか、島への移住者なのかという点でも、島の課題や魅力の捉え方は変わってくるようでした。
― 今回のことがきっかけで、島民の方々も島づくりへの取り組みを始められたわけですね?
島津:フィールドワークに行く前は、最終的に私たちの方で健康課題を解決するアクションプランを提示する予定でした。ですが、実際に島に行って現地の方々とお会いする中で、それはやめようということになりました。外から来た人間が「皆さんの課題はこれこれこうですから、こんな風に改善していってください」というのは、押し付けがましくてちょっと違うかなと思ったことが理由です。そのため、私たち学生が感じたことをそのまま、企画に協力していただいたことへの感謝も込めてお伝えしました。いわば恩返しというかたちです。それが結果的には島の方々のアクションに繋がったのかも知れないと思っています。
大谷:私は医療系の学生ではなく総合グローバル学部で国際協力に関する分野を学んできました。(注*大谷さんはすでに卒業し、現在は社会人)、実際にフィールドワークを経験してみて、地域診断のアプローチと国際協力には外部の人間が現地に入ってその地域の課題を解決しようとするという共通性があると感じました。島津さんも言ったように外部から解決策を提案することは、押し付けがましく一方的なアプローチとも考えられます。
今回は その点について考え悩みながら活動してきた中で、私たち学生の気づきを島民の方と共有することを地域診断のアウトプットとしました。結果として、島民の方々と島の暮らしや島のこれからについて話す機会を作ることができ、私自身大変勉強になりました。
大谷:私は医療系の学生ではなく総合グローバル学部で国際協力に関する分野を学んできました。(注*大谷さんはすでに卒業し、現在は社会人)、実際にフィールドワークを経験してみて、地域診断のアプローチと国際協力には外部の人間が現地に入ってその地域の課題を解決しようとするという共通性があると感じました。島津さんも言ったように外部から解決策を提案することは、押し付けがましく一方的なアプローチとも考えられます。
今回は その点について考え悩みながら活動してきた中で、私たち学生の気づきを島民の方と共有することを地域診断のアウトプットとしました。結果として、島民の方々と島の暮らしや島のこれからについて話す機会を作ることができ、私自身大変勉強になりました。
― 阪本先生と奥先生にお伺いします。今回の取り組みをどう評価されますか?
阪本:プライマリ・ケア医がその他の職種の人たちとチームを組んで地域を深く知り、個人の背景や価値観を踏まえながらケアをしていくというのは本来の姿なのですが、日本ではそれが十分できていないという現実があります。それを学生さんのレベルでここまでやり遂げたということがまず素晴らしいですよね。地域医療に興味を持ち、地域診断にしっかりと取り組み、それを恩返しという形で地域にフィードバックする。みんなで力を合わせながら真摯に向き合う姿勢には感動させられました。
余談ですが、島津さんが受賞した時、ちいここの代表の橋本さんが涙を流して喜んでいた姿が印象に残っています。
ちいここでは、とてもいい関係性が築かれてることが伝わってくるシーンでした。
余談ですが、島津さんが受賞した時、ちいここの代表の橋本さんが涙を流して喜んでいた姿が印象に残っています。
ちいここでは、とてもいい関係性が築かれてることが伝わってくるシーンでした。
奥:私はいつもちいここの学生の皆さんの気づきのパワーには元気づけられています。彼らは本当に積極的に地域の人たちのことを知ろうとしてくれるんですね。知るということは関わるということですし、関わるということは変わるということだと私は考えています。今回はまさにその好事例で、学生さん自身も島民の方々も互いに関わることでいい方向へと変わりました。その意味でもとても素晴らしい取り組みだったと思います。今回の経験をぜひ今後の活動につなげていってほしいですね。
― 最後にちいここの代表の橋本さんと副代表の上西さんからも一言いただけますか?
橋本:ちいここで、オンラインの力も使いながら、全国で合宿を実施したいと思ったのは、「医療系学生が、素直に想いを共有できる場をつくりたい!様々な暮らし、地域のあり方、生き方から自分の生き方にも向き合いながら、どのような医療者になりたいのかを、自由に感じて、考えられる場をつくりたい!」そんな想いからでした。たくさんの方々があたたかく受け入れてくださったおかげで、多くの地域で合宿をさせていただき、みんなで学びを深めてきました。活動を続けるうちにメンバーも増え、今回の企画を実現してくれた島津さんのような心強い仲間も加わってくれました。今回、私たちの活動が学術大会で認めていただけたことは、いろんな意味で感慨深いものがあり、受賞が決まった時はうれしくて思わず涙が溢れてしまいました。仲間や関わってくださる方が増える一方でリーダーとしての未熟さを感じていた中で、今回の受賞となり、取り組んできたことへの評価をしていただけたことの嬉しさと、仲間や関わってくださっている方々への感謝の気持ちで胸がいっぱいでした。これからもこの活動は、関わってくださるみなさまと一緒に、カタチを変えていきながら発展していくことを心から願っています。
上西:私たちのこの活動は大学のカリキュラムではなく、学生が学生なりに「こういうことって学んでおいたほうがいいんじゃない?」という思いをベースに続けてきました。将来、医療者となって働く上で何を大切にしていかなければならないかを模索しながら続けてきた面があります。実はこれまで「そんな活動って意味があるの?」「もっと医学的な知識の勉強をしたほうがいいんじゃないの?」と言われることもあり、多少の不安を覚えながら活動を続けていたのですが、今回のように学術的に評価をいただけたというのは、一つのターニングポイントとして今後私たちが自信を持って前に進んでいける励みになったと感謝しています。これからもいろんな方とのつながりを大切にしながら活動を続けてきたいと思っています。
参考)
医療系学生コミュニティ
「ちいここ~地域と医療のすべてがここにある~」
https://chiicoco.com/
Instagram: https://www.instagram.com/chiicoco_chiiki_iryou
X: https://x.com/chiicoco_iryou
「ちいここ~地域と医療のすべてがここにある~」
https://chiicoco.com/
Instagram: https://www.instagram.com/chiicoco_chiiki_iryou
X: https://x.com/chiicoco_iryou
最終更新:2024年12月09日 00時00分